4月より開催しておりました、企画展『縄文土器入門~縄文土器の特色をさぐる」展示資料の人気投票イベント『第5回 長岡縄文土器グランプリ』は、6月30日(日)をもちまして終了いたしました。
以下に、得票数の多い順に1位から8位までの縄文土器をご紹介します。
ご紹介する土器たちは、企画展『縄文土器入門』において8月24日(日)までご覧いただけます。
多くのみなさまにご投票いただき、誠に有難うございました。(有効票数1,497票)

第1位
大木(だいぎ)8b式土器(深鉢)
【400票】
縄文時代 中期中葉
長岡市 中道遺跡 出土
高さ 約 53cm
栄えある第一位は、ひときわ豪華な装飾と堂々とした佇まいのこの土器です。
突起や胴部の連続・連結するようなうずまきは大木式土器によくみられ、新潟の土器にも影響をあたえました。立体かつ中空の突起に、縄文人の粘土に対する深い造詣と技術がうかがえますね。
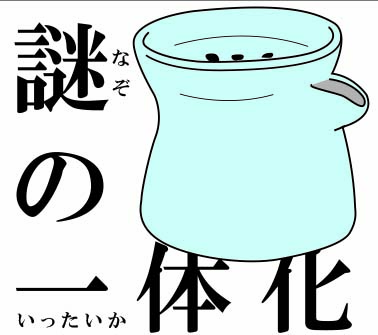
第2位
多孔底(たこうてい)付注口土器
【225票】
縄文時代 後期中葉
長岡市 中道遺跡 出土
高さ 約 11cm
第2位は、「使ってみたい!」人が続出した「多孔底付注口土器」です。茶こしやザルときゅうすを合体させたような珍しい土器で、新潟県から東北地方にかけて発見されています。ろ過用と考えられますが、何を?どうやって?そしてなぜ一体化?…興味がとまりません。

第3位
三仏生(さ(ん)ぶしょう)式土器
【163票】
縄文時代 後期中葉
長岡市 中道遺跡 出土
高さ 約 8cm
第3位のこの土器は、花びらのような飾りのかわいらしさで人気をあつめました。
花びらのような飾りは片側にしかないので、この土器は使う、または置いておく「向き」が決まっていたのかもしれません。表面もツルツルに磨かれた、美肌の土器です。

第4位
三十稲場式土器(蓋)
【156票】
縄文時代 後期初頭
出雲崎町 矢郷橋遺跡 出土
高さ 約 10cm
だれもがかぶりたくなる、この土器が第4位にランクイン!
実際には、縄文土器としてはめずらしいおナベのフタなので、「かぶせる」という発想は自然かもしれません。馬高遺跡と一緒に史跡指定されている、三十稲場遺跡から名付けられた土器型式のものです。
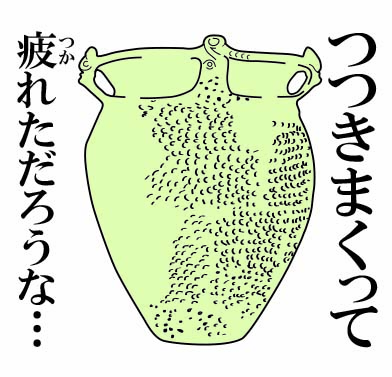
第5位
三十稲場式土器(甕)
【144票】
縄文時代 後期初頭
長岡市 十二遺跡 出土
高さ 約 43cm
第4位にひきつづき、三十稲場式土器のおナベの方が第5位でした。
土器の表面を棒などでつつく、つつく、ひたすらつつく…この文様が三十稲場式土器の特徴の一つ「刺突文(しとつもん)」です。高さ40cmをこえる土器をまんべんなくつついた縄文人さん、お疲れ様でした。

第6位
大洞(おおぼら)A式土器
(台付浅鉢) 【143票】
縄文時代 晩期後葉
五泉市 矢津遺跡 出土
高さ 約 10cm
1票差で第6位となったのは「使ってみたい!」シリーズ、台付浅鉢です。縄文時代の終わりごろにつくられた脚付きの盛り付け皿で、東北地方の亀ヶ岡式土器系統のものです。「使ってみたい」だけでなく「つくってみたい」という熱心なファンも見受けられました。
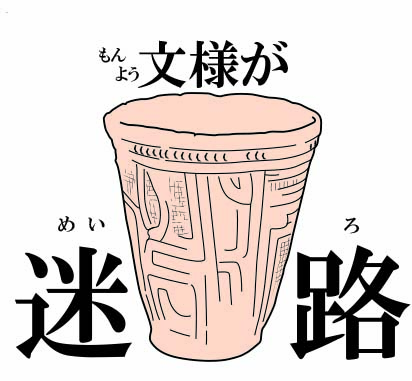
第7位
北陸系土器(深鉢) 【138票】
縄文時代 中期前葉
長岡市 千石原遺跡 出土
高さ 約 15cm
迷路のように不規則な線の間を格子状の文様が埋める、北陸地方の影響をうけた土器が第7位です。
不規則な線は半分に割った細い竹でつくられ、この工具は火炎土器の文様を整える工程にも使われました。
小ぶりながら、新潟と北陸のつながりを教えてくれる味わい深い土器。

第8位
台形土器 【128票】
縄文時代 中期
長岡市 岩野原遺跡 出土
高さ 約 9cm
第8位は、妙な迫力を感じさせる謎の土器。通常の土器とは逆に、底がなく、てっぺんがふさがっています。発見例が少なく、用途も「ものをのせる」「なにかをつくる」台、ではないかといわれていますが、はっきりしません。謎とともに妖気すら感じさせるビジュアルも、少数の熱狂的ファンを生みました。
